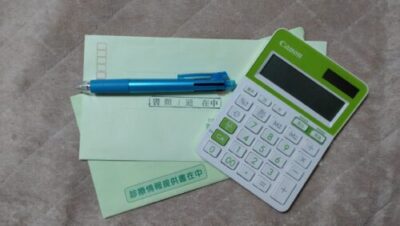ケガをして後遺症が残った場合、傷害保険などに加入していれば障がい給付金が支給されます。
先ず、かかっている病院に症状固定を受け、保険会社から所定の「傷害保険後遺障害診断書」や「障害診断書」等(保険会社によって呼び方が異なる)を受け取り病院で記載してもらいます。保険会社でそれらが審査がされ1~3週間ほどで後遺障害の等級に応じた支給金額が決定されます。
後遺障害の等級に当てはまらまかった場合は、不支給となりその理由が書かれた書類と診断書に要した金額のみが返金されます(日本生命、明治安田生命の場合)
不支給となった場合、納得のいかない方も多いかと思います。
明らかに所定の障害状態に当てはまらない場合は致し方ないとしても、実際の後遺症が重く結果を受け入れられない場合、まだ出来る事は残されています。
夫の後遺障害申請で不支給の通知を受けっとた時、私がしたことをお伝えしたいと思います。
(以下は明治安田生命とのやりとりで、頚髄損傷による四肢麻痺などの後遺症の申請の例です。)
保険金・給付金のお支払いに関する通知
手紙の1枚目には最初に、支払いできない旨の結果とお見舞いの文章が書かれていおり、
次に支払われる場合の所定の障害状態について説明書きがありました。
障害給付金は、災害特約の責任開始期以降に発生した不慮の事故による障害を直接の原因として保険期間中に添付の「給付割合表」に定める障害状態のいずれかになられ、回復の見込みがなく、症状が固定した場合にお支払い対象となります。(明治安田生命より引用)
さらに今回の請求は頚髄損傷による四肢麻痺であったため、四肢関節の障害について書かれています。
「四肢関節の障害におきまして、お支払いの対象となる障害状態は『関節の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下になった場合』と規定されており、このたびのご請求では、生理的運動範囲を以下の前提で判断させていただきました。」
と記され、各関節ごとの既定の数値が書かれていました。次に、提出した書類の結果ということで診断書に書かれていた各関節ごとの数値が比較して記載してありました。
二つを比べた結果として、四肢関節の運動範囲が2分の1以下に至っていないため、支払いの対象とはならないと再度述べられていました。
介護状態にも触れられていて「食物の摂取、排便・排尿・その後の後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴の殆どが自力では困難で、その都度介護を要する状態」に該当しないとの判断でこちらも給付の対象とはなりませんでした。
よくよく読むと、本人の今の状態と関節の可動域の数値があっていないような気がして実際に動かしてもらうと、素人目線でしかありませんが規定の2分の1以下しか動いていない箇所があるように感じ疑問に思いました。
ご請求相談センター
通知書と同封されていたものに、診断書にかかった費用を請求する用紙、身体障害の給付割合表(障害給付金の支払対象となる障害状態を規約から抜粋した表)があり、もう一枚【ご請求相談センター】の案内の用紙が最後につけられていました。
それは相談に関しての段階が3つに分けられていました。
①ご請求相談センターによるご説明
ご請求、ご照会の結果、死亡保険金・入院給付金等のお支払いを受けられなかった場合のお問い合わせやお申し出は、「ご請求相談センター」が承ります。
②支払相談室によるご説明
ご請求相談センターによる説明でご納得いただけない場合には、支払査定部署とは独立した「支払い相談室」の専門スタッフが、お電話にてご説明させていただきます
①、②で納得できない場合、社外弁護士とのご相談制度をご紹介いたしますとのことで、
③保険金・給付金のお支払いに関する不服申立制度
社外弁護士とのご相談制度の不服申し立て制度事務局をご紹介します(別途申込要)
との記載がされており、③の社外弁護士との相談に関しては東京で直接面談、名古屋、大阪の相談センターまたは所定の支社でテレビ会議システムによる面談が可能であり、費用は交通費以外は無料とのことです。
その時したこと
①「ご請求相談センター」に電話を掛ける
さっそく「ご請求相談センター」に電話をかけ納得いかない旨を伝えるも、紙面に書いてある通りの事を再度詳しく説明されお支払いは出来かねるとの返事でした。
実際の症状はもっと重くて可動域も半分以下の関節も見られるんだと訴えるも、「こちらとしては、診断書を見ての判断しか出来ません」とのこと。
「しかしながら、今現在、症状が悪化していらしてお支払い対象に該当すると認められれば保険金はお支払することが出来ます。そのためには新たに診断書の提出が必要です。」とも言われました。
なるほど、、、もう1度測定をやり直して医師に新たに診断書を書いてもらう必要はあるが今後一切お支払しませんという訳でなさそうです。
私が申請した診断書の測定値は提出する1か月ほど前の測定で、体が一番回復して絶好調のときのものでした。その時は後から体の拘縮や疼痛の増悪が起きるとは考えもしませんでした。
本人の希望もあって測定後間もなくして退院となりました。
入院中は午前と午後に各々90分程手厚いリハビリを受け、時間があれば許可を取り病院の設備で自主トレーニングを行うこともできたのに対し、退院してからは週に2回から3回、30~40分程のリハビリを受けることしか出来ませんでした。
週に約20時間程あったリハビリが、週に2時間程になったのと疼痛の増悪で自主トレーニングも思うように出来なくなっていたため、筋力は落ちそれに伴い可動域も悪くなっていると思われました。
そこで、再度申請したい旨を伝え新たに申請用紙を送って頂くようお願いしました。
今後の生活に不安ばかりが大きく心に余裕が持てなくなっていてた私は、申請のチャンスは1度しかないと思い込んでおり、審査の結果にパニックに陥っていました。
相談室に電話をかけて一先ず安心しました。
②新たに診断書を書いてもらう
入院していた病院に電話をかけ、保険請求に使う診断書をお願いしました。
その時に、前回より体の動きが悪くなっている様なのでもう一度測定からやり直して頂きたいとも伝えました。
そして測定法についても厚かましいとは思いましたが、アレコレお願いしました。
前回測定されていなかった項目(左右の手指・足趾の運動障害、脊柱障害、反射異常)を増やしてもらったり、麻痺部分を斜線で表す部分の漏れを指摘したり、疼痛について詳しく備考欄に記載してもらうように伝えました。
これらがどれだけ役に立ったかは分かりませんが、思い付くことは全てお願いしました。
測定中も付き添い、測定項目を増やしたいことを再度伝え、バビンスキー反射、ホフマン反射などまで調べて頂きました。
やはり運動機能は落ちており測定値は殆どの項目で下回っていました。
念のため「可動域は動かないふりとかしたら分かるものなんですか?」と尋ねると
「スグにわかりますよ、他動域を測定するときにひっかかりがあるんですよ。ググっと抵抗があって感じかたが違うんです。」とのことで少し安心したのを覚えています。
と言うのもズルをしていると思われてたら嫌だなぁと内心思っていたからです。
なので敢えて測定中は保険の申請で非該当だったことは伝えていませんでした。測定後に実は…と打ち明け細かく測定をお願いした訳と医師に備考欄への詳しい記載を頼んで頂くようお願いしました。
③診断書の確認
2週間ほどで診断書が出来上がり受け取りに行きました。
その際忘れてはならないのは、診断書のコピーを必ずとっておくという事です。
前回もコピーを取っていたことで保険会社の方と話す際に診断書のコピーを見ながら説明をうけたり、どの項目が測定されていたかなどを知ることができました。
後は、出来てきた診断書を隅から隅までチェックすることです。
今回は3社分の保険会社の診断書を頼んだのですが、やはり人のする仕事ですので漏れやミスはあるものです。麻痺のある箇所の斜線が書かれていなかったり3枚のうち1枚だけ測定値が数か所違っており記入ミスを見つけることが出来ました。その書き換えで更に1週間待たされることとなりましたが間違った測定値の診断書を出すことを思えばひと手間は必要だと思います。
さて、やれることはやりました。後はきれいに封をして提出するのみです。
結果
最初に申請書を出したのは確か4月の下旬頃で、5月末に支払いは出来ないとの通知を受け取りました。7月に再度測定をお願いし新たな診断書を提出できたのは8月位だったでしょうか。
9月に入り送られてきた結果は上肢、下肢、脊柱に後遺障害が認められ遅延利息とともに保険金が支払われました。
保険の請求をする前に体が不自由になった夫が生活しやすいように、先ずトイレの改修をしました。
おしりをきれいに拭くのが難しかったためウォシュレットが必須でしたし古い便器は高さが低く立ち座りがしづらかったからです。費用は約18万程。退院に合わせ早急にリフォームする必要があったため助成金などは受けていません。
お風呂も古く段差があり手すりも全くない状態でした。しかしながら風呂を新しくするとなると150万超の費用が掛かります。後付けの手すりや介助用の台を利用して私が一緒に入り介助することでやり過ごしていました。
ですので、保険金が下りた時に先ず思ったのが「お風呂がリフォームできる!」でした。
それらが叶うほどの保険金が支払われたのです。さらに脱衣場や廊下に手すりも付ける事が出来る金額でした。
保険に加入していてこれほど良かったと思ったことはありません。
まとめ
前提として診断書のコピーを必ずとっておくことです。これは今後、障がい者手帳や障害年金を申請する際にもとても役に立ちます。
診断書の封が閉じられていることもありますが、開けたから無効になるといったことはありませんでした。保険会社に診断書を提出するともう戻っては来ませんので申請をする前にコピーをとることをお勧めします。
後遺障害保険金が支払われなった時に私がしたこと
- 診断書のコピーをとっておく
- 支払われなかった際の書類によく目をとおす
- 疑問があれば相談窓口に問い合わせる
- 再申請する為の用紙を送ってもらう
- 病院に診断書を依頼する(測定項目の追加や備考欄への記入もお願いする。)
- 受け取った診断書を間違いや抜けがないかよくチェックする。
- 新たに受けとった診断書はコピーをとっておく
- 申請書の再提出
以上が私が行ったことですが、支払われなかった場合の相談としては比較的簡単で報われたケースだったと思われます。場合によっては更に深く相談が必要で弁護士を交えての話し合いとなる方もいらしゃるかもしれません。
多少の厚かましさも必要
今回の場合、診断書から判断するしかない保険会社には全く落ち度はありませんでした。
検査項目やそこに書かれた数値でしか後遺症の度合いは分からないからです。
ましてや、素人が見て何が必要な項目でどこからが後遺障害として認められるのかは規約を見たとしても判断できないいと思います。
かといって泣き寝入りすることはありません。少しでも疑問に思うことがあるなら対策をしようという前向きな姿勢が必要です。
問い合わせ窓口もちゃんと設けられています。今はインターネットで様々なことが検索できます。
頭を下げるべきことは下げ、多少厚かましいと思われるお願いもしてみることです。
最後まで諦めないで下さい。例えダメだったときも潔く諦めがつくというものです。
私の場合、本人の機能低下もありましたが、追加で測定をお願いした脊柱の項目が認められたのは本当に良かったと思いました。
障害給付金(身体障害の場合)は等級ごとに契約した保険金額に対し割合が定められていて、各部位ごとに支払われます。今回の場合、
第4級31 脊柱に運動障害を永久に残すもの 3割
第5級32 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 1.5割
第5級33 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 1.5割
と言った感じです。なんと後から追加でお願いした脊柱の項目が一番高い比率で保険金が支払われたのです。他の保険会社に再提出した分も同じ割合で支払われました。
普段の私は以外にも気が弱く、誰かにお願い事をするなんてことは滅多にしない性格です。でも今回ばかりは気持ちを奮い立たせて頑張りました。
一生に何度か頑張らないといけない事があるとするなら今でしょう!という気持ちでした。
保険金が支払われず涙をのんでいる方がいらしたとしたら諦めないで欲しいのです。
私にでも出来たのです。
頑張ってみて下さい。
~手続きいろいろ~( 傷害保険「障害給付金」非該当~その時した事~)